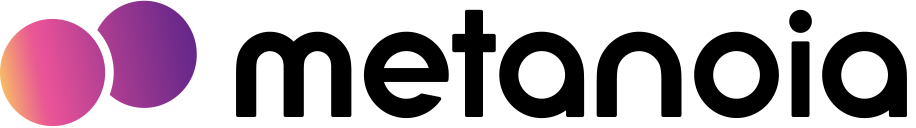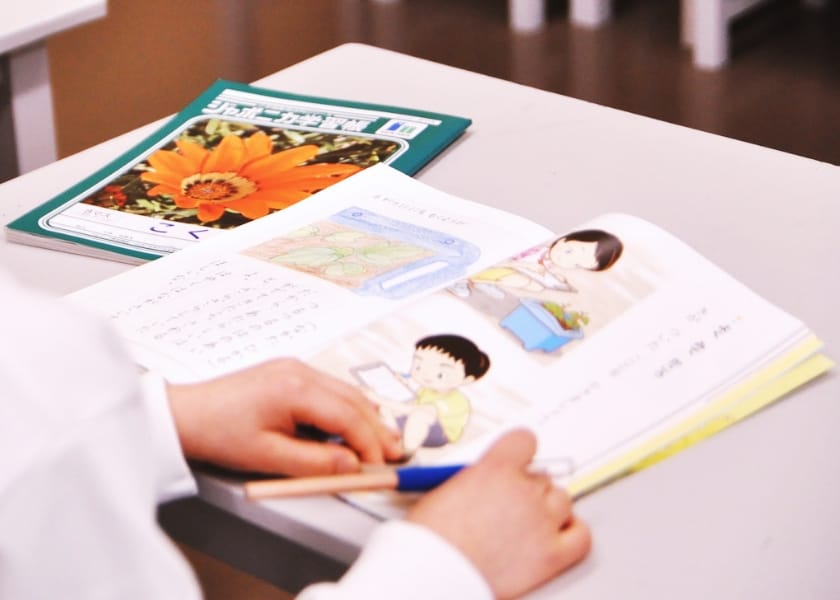2025.08.18
お知らせ
〈緊急発信〉子どもたちを差別から守る考え方・寄稿文:「命に順位はつけられない」—分断ではなく、連帯を育てるために
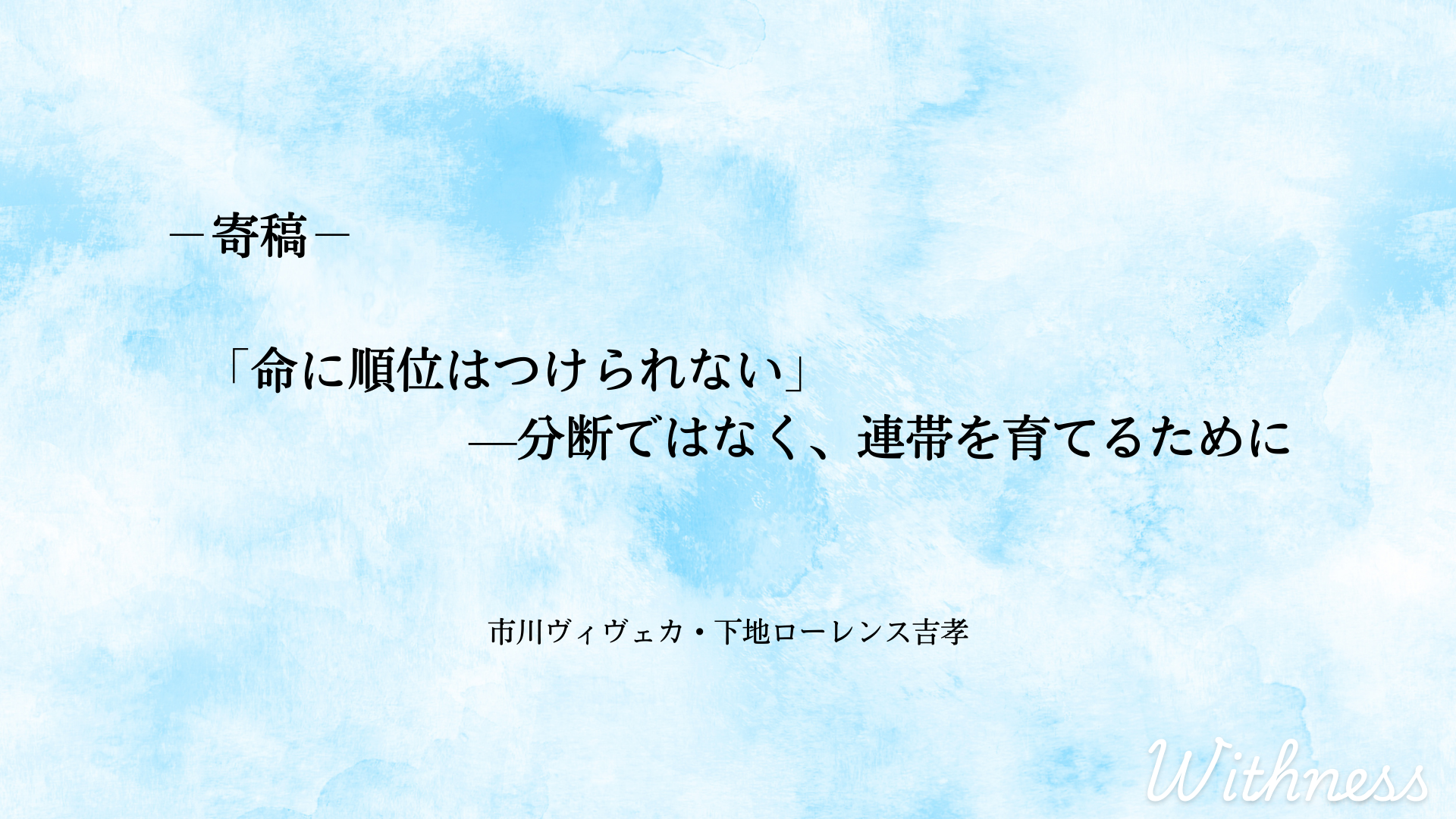
「外国人」と呼ばれる人々や、複数の民族・人種にルーツをもつ人々(「ハーフ」「ミックスルーツ」と呼ばれる人々)など、外国にルーツをもちながら日本社会で生きる多くの人々は、これまでも長きにわたり、差別や偏見の目に晒されてきました。
しかし先般の参議院議員選挙以来、「日本人ファースト」「違法外国人」など、特定の属性に基づいて人を線引きし、優劣をつける言葉を公の場で耳にする機会がかつてなく増えています。
そうした言葉は大人だけでなく、子どもたちの間にも届き、日常会話や行動に影響を与えます。
もし、身近な子どもがその言葉を口にしたら。
もし、その言葉で傷ついた子が目の前にいたら。
私たちは、これ以上、言葉による分断や傷つけ合いを広げてはなりません。
子どもたちを差別の被害者にも、加害者にもしてはならないと強く願っています。
子どもたちが、大人の言葉を真似て、知らず知らずのうちに誰かを傷つけてしまわないように。
傷つけられた子の心をこれ以上放置してしまうことのないように。
私たちは、何を伝え、どう寄り添うことができるでしょうか。
「そういう言葉を言っちゃだめだよ」と注意するだけでは、伝わらないかもしれません。
なぜいけないのか、どうして心が傷つくのか、傷ついた心をどのように修復していけるのか。
共に学び、考え、一人ひとりが行動につなげていく必要があります。
そんな思いから、今回、カウンセラー/社会福祉研究者の市川ヴィヴェカさんと、社会学者の下地ローレンス吉孝さんに寄稿をお願いしました。
子どもたちの育ちを支える先生方をはじめ、この社会に生きるすべての人へ。
ぜひお読みください。
寄稿者紹介
- 市川ヴィヴェカ:トロント大学博士候補生/社会福祉士/心理療法士/保育士
東京都三多摩生まれ。ミックスとして日本人の母のもとで育つ。
市役所の生活援護課に非正規雇用公務員として勤務後、現在、カナダでソーシャルワーク研究と多文化・多言語カウンセリングを行う。
専門は社会福祉。移民/難民/ミックスルーツ、多文化カップル・家族カウンセリング、トラウマなどを扱っている。
- 下地ローレンス吉孝
「ハーフ」や「ミックス」等と呼ばれる人々について研究している社会学者。現在は沖縄在住、沖縄大学・地域研究所・特別研究員。
著書に『「混血」と「日本人」 ―ハーフ・ダブル・ミックスの社会史』(青土社、2018年)、『「ハーフ」ってなんだろう? あなたと考えたいイメージと現実』(平凡社、2021年)、監訳・解説に『インターセクショナリティ』(人文書院、2021年)。「ハーフ」や海外ルーツの人々の情報共有サイト「HAFU TALK」(https://www.hafutalk.com)を共同運営。)
〈寄稿文〉 「命に順位はつけられない」——分断ではなく、連帯を育てるために
人の命に、優先順位をつけることはできません。
誰もが生まれながらに、かけがえのない存在であり、等しく尊重されるべき人間です。
けれど今、その「あたりまえ」が、脅かされる場面を目にすることが増えてきました。
ある人の権利は守られ、別の人の権利は後回しにされる。
そのような構造が、日常の中に静かに、けれど確実に浸透しています。
「日本人ファースト」という言葉を聞いたとき、どんな印象を持つでしょうか。
一見、自己肯定感や共同体意識を高めるようにも見えるこの言葉は、
実のところ、誰かを優遇し、誰かを後回しにしてもよいという「命への順位づけ」の思想を含んでいます。
戦争が始まるとき、権力者たちは必ずと言っていいほどこう言います。
「限られた資源は、まず我が国民のために」
「我々の土地や文化を守るために、他者を排除しなければならない」
その声の裏には、暴力、追放、殺害の正当化が潜んでいます。
それは歴史が何度も繰り返してきた事実です。
戦争のような極端な状況でなくとも、
「あの人は私たちとは違う」「“自分たち”が先に助けられるべきだ」という思考は、
日常の中でもじわじわと広がり、排除や差別として現れていきます。
その思考は、見えないかたちでこう問いかけてきます。
「誰が大切にされ、誰がそうされなくていいのか」
無意識のうちに、心や社会に“優先順位”が刻み込まれていくのです。
傷ついた心を前に、どうあれるか
無視されたり、雑に扱われたり、それに気づくことを「気にしすぎだよ」と言われる経験の積み重ねが、人の尊厳を、安心を、そして時には命までも脅かしていきます。
心肺停止の人に対して、私たちは迷わず「大丈夫?」と声をかけ、助けようとします。
けれど、日々差別やマイクロアグレッションにさらされ、心が傷ついている人たちには、なぜ声がかけられないのでしょうか?
「冗談だよ」「悪気はなかった」「気にしすぎだよ」——
そうした言葉が、誰かの心をさらに深く沈めてしまっているかもしれません。
心の傷も、命に関わる。
まずはそこに、想像力を向けてみましょう。
誰かが差別されている場面に居合わせたとき、「何もできない」と感じる人は少なくありません。
でも、ほんの小さな行動が、大きな支えになります。
• その場に一緒に立つ
• 「気づいていた」と後から伝える
• 話を聴く時間を差し出す
• 一緒にその場を離れる
それは、「助ける人」になるということではなく、横に並んで共にいる人になるということ。
それが、ウィズネス(withness)=共にある目撃者の姿勢です。
あなたにできる、小さなことから
差別を止めることは難しいかもしれない。
でも、「それ、偏見じゃない?」と問いかける勇気を持つことはできるかもしれません。
傷ついた人に「つらかったね」と言葉をかけること。
笑って同調しないこと。
誰かが見てくれていた―その一瞬が、沈みそうな心を支えることがあります。
差別の場で「何も言わない」ことは、実は中立ではなく、現状に加担してしまっているかもしれません。
どんな人でいたいか。どんな社会の一員でありたいか。
差別を許すことは、
自分の家が壊れていくのを、黙って見ているのと同じ。
私たちはみな、同じ屋根の下で暮らしているはずです。
食べ物が足りなければ分け合い、場所が足りなければ譲り合う。
丁寧に目を配り、手をかけ、声をかけ合う社会でありたい。
「人を大切にする社会」は、特別な誰かがつくるのではありません。
それは、私とあなたの、小さな選択の積み重ねから生まれていくものです。
どうか、目をそらさずに、隣に立ってください。
「他人事ではない」と思うことから、連帯は生まれます。
分断ではなく、つながりを。
沈黙ではなく、対話を。
排除ではなく、共に生きることを。
ここから、今から、はじめましょう。
ーーーーーーーーーーー
(参考)バイスタンダー「5D」から得られるヒント
救命救急の現場で、その場に居合わせた人(バイスタンダー)として取れる行動を可視化した「5D」。
誰かの心が傷つけられた現場に居合わせた時にも、この考え方を応用することができます。
・注意を逸らす(Distract)
・助けを求める(Delegate)
・記録する(Document)
・後からフォロー(Delay)
・直接伝える(Direct)
バイスタンダーとしての自分の立場や、その時の状況によってとれる行動は変わってきます。
それでも、いつでも、ウィズネス(Withness)のあり方を意識して、自らの言動を選択していきたいですね。
ぜひ下方の画像を印刷し、各学校や職場にて掲示ください!

寄稿者のお二人が登壇!オンラインイベントを開催します。
"差別や排除は、戦争や災害時などの極端な状況だけでなく、日常の中にも静かに、確実に浸透します。"
今回のオンラインイベント<差別から子ども達を守る 実践講座 ここからはじめる連帯のつくりかた>では、
実際の場面を想定しながら「沈黙から対話へ」「分断から連帯へ」と向かうための視点と実践方法を、寄稿いただいた市川ヴィヴェカさん、下地ローレンス吉孝さんをお招きし、「ウィズネス」「バイスタンダー」などの視点から共に考えます。
どなたでも参加可能です。子どもたちの育ちを支える先生方、教育関連の職員の方々の参加を歓迎します!
お申し込みお待ちしております。
<詳細・参加申込はこちらから>
・9月5日(金) 20:00〜21:00
・開催方法:zoom(ウェビナー)
・参加費無料、申込者は後日アーカイブ配信あり
・当日参加者は質疑応答への参加可能!

マンスリーサポーター募集に関するご案内<9月30日まで 目標500人!>
認定NPO法人メタノイアは、外国につながる子どもたちへ日本語学習の機会を届ける日本語教室の運営、日本語教師等外国につながる子どもたちと関わる方々の育成、外国につながる子どもたちの実態について社会へ発信する活動を行う団体です。
「分断ではない」方の社会づくりに参加いただける仲間を増やすため、現在マンスリーサポーター(継続寄付者)募集キャンペーンを実施中です。
子どもたちに差別や分断ではない、互いの命と尊厳を守り合える社会を引き継いでいくために、あなたの参加をお待ちしています。
<特設ページはこちら>